なまはげおじさんです、こんにちは。
君津のさくら塾のブログへようこそ。
今日はテストのお話。
大成功!
さくらっ子の1学期定期テスト、
結果について
実施時期について
出題範囲について
問題について
この4つのテーマでまとめます。
結果について
3年平均 436.3点
国語 77.5点
社会 89.8点
数学 94.3点
理科 86.3点
英語 88.5点
2年平均 435.2点
国語 80.2点
社会 93.0点
数学 89.0点
理科 88.4点
英語 84.6点
1年平均 433.0点
国語 85.7点
社会 88.7点
数学 81.7点
理科 91.7点
英語 85.3点
3年生は数学がよかったですね。
英語も90点台にのせたいところ。
2年生は、学校によっては問題数の多すぎる教科がありました。
英語は個人差が大きかったかな。
1年生はよく踏ん張りました。
数学と英語、頑張らないとね。
5科計自己記録更新は5名、
ごほうび対象は今のところ1名。
※さくら塾の定期テストのごほうび
いずれか1つに該当した人が対象
・100点満点獲得
・5科計475点以上獲得
・学年順位上位5%
学年順位の発表はこれからなので、ごほうび対象者が増える可能性アリ
※データを開示しているのは、塾をお探しの方にさくら塾のイメージをつかんでいただくためです
実施時期について
今回は、5月に修学旅行に行った関係で、体育祭の実施が他校より1~2週間遅くなった学校がありました。
このエリアでは、出題範囲表が配布されるのはテスト実施日の2週間前。その日からテスト期間となります。
つまり、その学校では、テスト期間に体育祭を行うことになったわけです。先生方も生徒のみなさんも、いろいろ大変だったようで。
旅行会社の都合もあるんでしょうけど、やっぱり修学旅行を1学期にブチ込むのはやめた方がいいんだろうなぁ、なんてことを思った次第。
出題範囲について
毎回さくらっ子が悩まされているのが、出題範囲の変更です。
直前になって、
「範囲を縮めます」
と先生方から告知されるアレですね。
今回ね、ほとんどなかったんですよ。
範囲表に沿ってコツコツ頑張っている生徒が
「勉強してたのにカットされた」
「なんかソンした気分」
とふくれるようなことは、あまり起きませんでした。
先生方、ありがとうございます。
そうそう、出題範囲について、ふれておきたい話題があります。
教科書です。
今年使われている教科書は、昨年度までのものとは異なるものです。
小改訂版。
とはいえ、ちょっとレイアウトが変更されているだけ、ではないんです。
どの教科もだいぶ中身が変わりました。
最も注目された教科は、理科です。
この教科だけは、小改訂どころか、別の出版社のものに切り替えなければならなかったんです。
※くわしくは『中3になると理科の教科書が別の会社のものになるってホント?』という記事をご覧ください。
「教科書なんて、どこの出版社でも同じことが書いてあるんでしょ?」
と思ってるあなた、それは正しくもあり、間違ってもいます。
太字の用語も微妙に表現が異なっていますし、現象についての説明もその出版社のカラーを感じますが、だいたいのところで大きなズレはありません。
しかし、1点、現場の先生方に影響を与えていることがあります。
それは、単元の掲載順が出版社ごとに異なることです。
2年理科を例に挙げますと、昨年度までの第1単元は化学でした。しかし、今年採用された教科書では、生物なんです。
これには中学校の先生方も迷ったようです。
例年通りの順序で進めるか、
教科書順にあらためるか。
さくら塾では、2年生は4校から集まっていますが、教科書掲載順を無視して化学から始めたところが3校、教科書通りが1校。近隣校なのに、中学校ごとに学習している内容が異なっています。
つまり、出題範囲もバラバラで……。
授業のやりにくいことったら(涙
いや真面目な話、引っ越しなどで転校することになったら、「生物をもう一度学習することになってしまって、化学は学ばないままでおしまいになる」なんてことも起きちゃうんですよね。
君研なんかで「進める順序を統一しようよ」なんてお話は出なかったんでしょうかね。
問題について
某中学校の2年国語で、とても興味深い出題がありました。
次の文章をそのまま解答用紙に書き写せ、というものです。
私は思わず、
「え……?」
なんていうおかしな声が出てしまいました。
「誤字・脱字さえしなければ誰でも満点とれちゃうだろうに、どうしてこんな問題を出したんだろう」
なんて思ったんですが、ウチの生徒はまさに誤字・脱字だらけで、ハチャメチャに減点されていました笑
興味深いことに、このさくらっ子は5科計450点を超えているんですよ。勉強がひどく苦手なわけではなく、反抗期真っ最中で「テストなんてどうでもいい」なんて態度だったわけでもないんです。
文章をそのまま書き写すことができなかったんです。
ほかの中学校では条件付き作文を出題しているところを、あえて書き写しの問題を選んだわけですよ、某中学校の国語科の先生は。
この先生は、おそらく、書き写すことができない生徒が多いことを予想していたんだと思うんです。
だからこそ、こんなユニークな問題を出題したのでしょう。
私ね、日頃から学年の生徒たちのようすをしっかり観察していらっしゃる先生なんだろうな、なんて感じたんです。
何かの場面で、「この子たちは、そもそも書き写すことができないのではないか」と感じることがあり、そのことを心配なさったのでしょう。
今回の出題は、
「君たち自身はこのことに気づいていますか」
という、生徒のみなさんへの投げかけなのかな、なんてことを考えました。
中学生の学習を指導する者として、私はこの先生のファンになりました。
塾のおじさんとしては、この問題の正答率(得点率)がちょっと気になっています。
1学期のテストはこれにておしまい。夏にみんなで頑張って、飛躍の2学期を迎えたいと思います。
それでは今日はこのあたりで失礼します。どうぞ健やかな一日をお過ごしください。


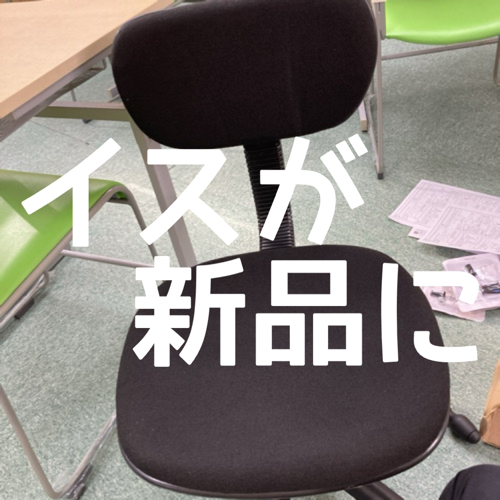
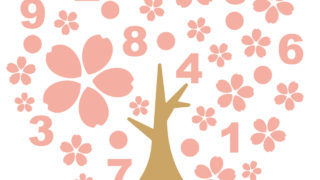
この記事についてのコメント